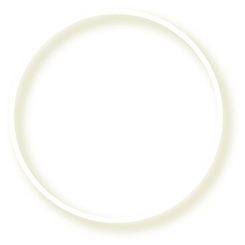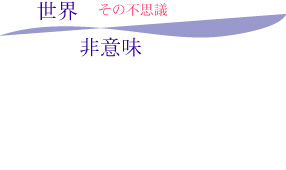
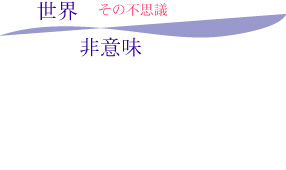

|
それ、は、文字通り、それ以上でも以下でもない、それ、です。まことに不可 思議です。世界の外や中、上や下、そのようにありません。人によって違うものでも、ありません。尚、とある権威に無関係。不自由に無関係。信じることにも、無関係といいます。
総てに浸透する、否。総てを排除しない、否。いまここ、否。それである実在、諾。そのようにあります。 それは世界を超えている、との理解。おそらくとても、困難ではないでしょうか。なぜなら人は、世界を生きるものであるからです。 道標はことごとく否定されざるを得ないのであり、なお変わらないものとは、世界と思われる世界、でなく、ただ眼耳鼻舌身意、自己と世界の仕組み、その機能です。 自身と世界の有無とは、どちらでもあり・・・どちらでもない・・・どうとも表現不可能、それだけです。ここで初めて、世界は偏見に満ちた否定に晒されることがなくなるのであり、人は、仕組みを仕組み、愛は、愛。であることを見ます。 偏りを超え、その、わたくし、であること。それは、世界と自己の仕組みは仕組みとして、確かに不可分なく成立していることの了解です。意味は過剰に、ありません。ここで再び逆に戻り、それを世界に照らし合わせる堂々巡りは起こりません。不可 逆。それは、それ、として成立しています。物事を追って関係付けるのは、世界の、ことさら自我の作用であることが理解されます。 人は不可知への飛躍を、人生に於いて「経験」することで第一義が通ります。第一義とは、それ自身による自身であることです。それは体験です。正確にいうならば、その経験が体験に降りることによって人は気付くことが可能です。「自己」を見ることが起きるとは、それまでの日常をまったく超越する、体験であり、なにより「経験」です。そして理解する過程があります。 その過程は過程として、ことさら消し去られることなく、隠されることなく、着色せず生きるとは、人が自己で在ることの大事な経緯です。人は、嘘を、とくことが、できません。 幸いとは、それは人に起こるものでありながら、起こすものでも、あることです。 |
|
人に、知的理解のみでない体験的その変容が起きたなら、身口意に偽りを保つことは難しいのです。人に第一義が通るとき、意識と世界の構成要素とは無関係の、それ、が人を生きるといえます。それを、法、とも、言うことができます。 人の変化が世界の範疇に留まるとき、非常に、或いは如何に素晴らしい共感であっても、真善美であっても、移ろいゆく時空に於ける変化に属しており、世界の何かに作用されざるを得ません。その体験と理解は、正しい位置に入ることができないのです。 ここでは知覚が主となり、見るものは自分となり、その偏り故に、ときに不要に人を痛めるものでもあります。世界は鏡、見るものは自分、を正しく使うためには、人はそこを超えていなければなりません。変容が世界の範囲内である、たとえばなにか共感、なにか一体化、すなわち、知覚の範疇にあるとき、人は、法に至ることができません。 体験が、世界の構成要素を超えて確かであればあるほど、人は、「できないことはできない。」。たとえば、感情がどんなに焦れても、状況が完全にそれを勧めているようにみえても、’それであることによって’嘘をつくことができない、’それであることによって’盗むことができません。 理由なく、そう、であること。理由なく、嘘をつかない、盗まない。変容を経て尚、これが意識には容易でありません。意識は、その感覚、感情、思考・・世界の構成要素の総てに対応しているからです。 人は、ここを全的に超えるとき、知識による理解からではでなく、その身口意とは、意識に上るまでもなく、矛盾でないのです。 法。それはまた、「いいわるいではない、善いを。」 とも、 言い換えることができます。 |